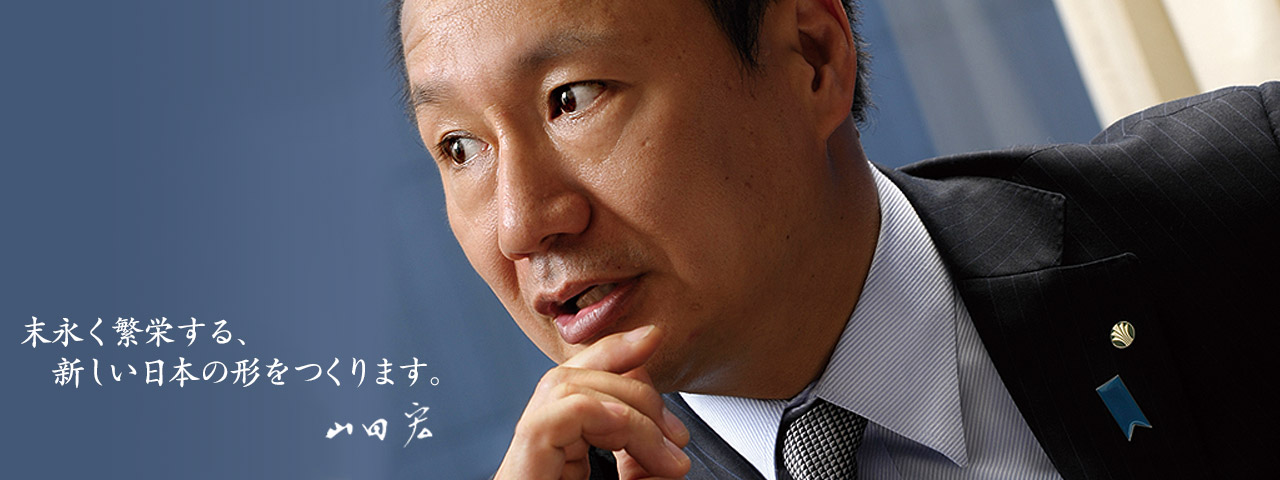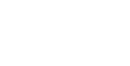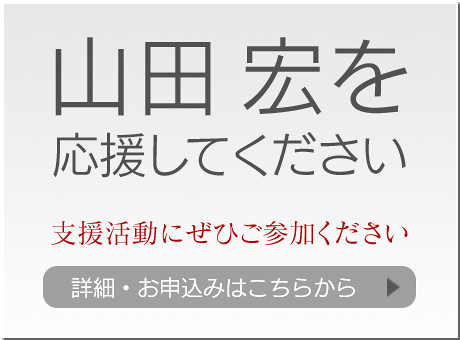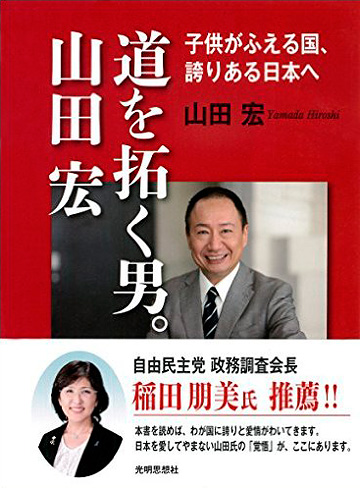我々は中国といかに付き合うべきか――杉並区長が語る憂国の決意
唇歯輔車(しんしほしゃ)という言葉をご存じだろうか。
紀元前六五五年の中国・春秋時代。晉(しん)の献公は小国の(かく)を討とうとしたが、そのためには、と同盟関係にある虞(ぐ)の国を通らなければならない。そこで虞公に名馬と宝玉を贈り、晉軍の領内通過を認めてほしいと要請した。虞の賢臣は「諺にも『輔車(頬骨と歯茎)相依り、唇亡ぶれば歯寒し』と言います。虞とは輔と車、唇と歯のような関係であり、晉軍の通過を許してはなりません」と諫言したが、虞公は贈り物に目がくらみ、通過を許してしまった。果たして晉軍は、を討った帰途、虞も攻めて滅ぼしてしまったという。
この故事来歴を想起させるような出来事が、年明け早々にあった。学習教材大手の学研グループが中国の圧力を受け、地球儀上の台湾(中華民国)の表記を「台湾島」としていた問題である。
■幻の記者会見
インターネットのニュースでこの問題を知った一月十日、私は、ある決意を抱いて登庁した。そして、杉並区と学研との取引状況を調べさせた上、区の幹部を呼んでこう言った。
「区内の小・中学校で今後、学研の副教材などを購入しないようにしたい。明日にも記者会見して発表するので、準備して下さい」
幹部は、「またそんな物議を醸すことを」と当惑した様子だったが、この時の私の指示は、冷静かつ正当なものだったと今でも思っている。外国の圧力に屈して、日本の国益に反するような教材を販売する会社を、学校教育から遠ざけるのは、自治体の長として当然の処置だからだ。
報道によれば問題の地球儀は、中国の工場でつくられていた。台湾を「台湾島」と表記しただけでなく、音声案内でも「中華人民共和国」と表現していた。批判を受けた学研は、「中国側の指示に従わなければ輸出できないと言われた」と弁明したが、目先の利益のために、国益を顧みない行為だったと言わざるを得ない。親日派の多い台湾の人々が日本に来て、この地球儀を目にしたなら、どんな感情を抱くだろうか。日台関係にひびが入る――それが中国の狙いかもしれないが――恐れも十分あるのだ。
もう一つ、この地球儀で見過ごせないのは、北方領土以北の千島列島と南樺太を、ロシア領として色分けしていたことだ。周知の通り両地域は、日ソ中立条約を一方的に破って侵入してきたソ連が、火事場泥棒的に奪い取ったものである。日本はサンフランシスコ講和条約の際、やむなく領有権を放棄したが、ソ連の強盗行為までは認めておらず、帰属先を未定としている。このため地理の教科書では、両地域を日露のいずれにも属さない白色にしている。にもかかわらずロシア領に色分けするのは、国家に対する裏切り以外の何物でもない。
たかが地球儀一つで大袈裟なと、軽く考えてはならない。言うまでもないことだが、地図はその国の利益に直結する。
例えば尖閣諸島の問題。中国側は領有の根拠として、江戸中期の経世家・林子平が天明五年(一七八五年)に著した三国通覧図説の地図に、尖閣諸島が中国領として色分けされていたことを挙げる。日本の高名な学者ですら昔は中国領と認識していたではないか、というわけだ。これに対し日本側は、中国が尖閣諸島の領有権を主張するようになったのは地下資源が確認された一九七一年以降であり、それ以前の中国政府発行の社会科地図には、尖閣諸島を日本領としていたではないかと反論している。
ほかにも、世界中で争われている領土問題の大半は、地図にどう書かれていたかが大きな争点になる。たかが地図一枚、地球儀一つでは済まされないのだ。
北方領土返還交渉の際、日本はソ連に対し、千島と南樺太のロシア領有を断じて認めないという態度をとることで、交渉を有利に進めることも可能だ。しかし千島をロシア領と色分けした地球儀が日本国内に出回っていたのでは、何の説得力も持たないだろう。
以上の理由から、私は学研に対し、厳しい対応が必要だと判断した。幸いにも学研は、問題発覚後すぐに態度を改め、販売中止と回収を決めたので、私は記者会見を中止した。
むろん私は、学研が反国家的な企業だとは思っていない。私の知る限り、創業者の故古岡秀人氏は、なかなかの愛国者であった。五歳で父を失い、貧苦に耐えながら育ち、官費で師範学校を卒業し、終戦直後の昭和二十一年、「荒廃した日本を再建するには次代を担う子供たちの教育が最も大切だ」として設立したのが、学研だった。
氏は後年、私財を投じ、母子家庭の子供たちを支援する古岡奨学会を設立した。その目的を「向上心をもって勉学に勤しもうとする志操堅固な者に対し、高校在学中の学費の一部を給与し、国家社会に貢献しうる人材の育成に寄与する」としたのは、氏の高尚な教育観を物語って余りある。
今回の問題で学研は、地球儀を販売していた子会社「学研トイズ」を解散したほか、グループとして地球儀の製作および販売を全面的に自粛する事態に追い込まれた。おそらく、一般からの苦情や批判が殺到したためだろう。
これを機会 に、学研が創業の理念に立ち返ることを、願って止まない。
■無為無策の文部科学省
一方、学研以上に許せなかったのが、日本政府の対応だ。一企業の問題として我関せずを決め込み、国内外に対し、何らステートメントを発しなかったのはどういうわけか。またしても中国が、我が国の教育に不当な干渉をしてきたのである。中国の対応は極めて遺憾であると、なぜ抗議しなかったのか。
ちなみに、中国側はすぐに反応している。中国外務省の副報道局長が一月十日の会見で、「中国で仕事をする会社は、中国の法律に従うべき」とのコメントを発した。台湾島の表記は当然であり、日本企業への干渉も正当であるとの立場を、内外の記者団にアピールした格好だ。これに対し日本が何も反論しなければ、中国の言い分を認めることになる。少なくとも世界はそう受け止める。
とくに文科省の対応には呆れるばかりだ。教材関連会社が解散するほどの重大問題なのに、一つのコメントもない。
文科省は昨年も、将来に禍根を残す大失態をした。沖縄戦集団自決をめぐる教科書検定のことである。軍の関与があったかどうかはさておき、検定結果が政治的圧力によって覆されるなど、絶対に許されるべきではない。
前文科相の伊吹文明氏は、検定に問題はないという方針を堅持していた。ところが渡海紀三郎氏が就任した途端、あっさり方針転換してしまった。沖縄県での「11万人」抗議集会など世論の批判を受けてのことだろうが、その結果は重大だ。日本の教育は圧力を加えれば変えられるということを、内外に晒すことになったのだから。
「諺に曰く、一年の謀(はかりごと)は穀を植ゆるに在り、十年の謀は木を植ゆるに在り、百年の謀は人を植ゆるにあり」とは、明治六大教育家の一人である新島襄が、同志社大学設立の趣旨として述べた言葉だ。教育とはまさに、国家百年の計であって、外圧に屈するのはむろんのこと、時々の国内世論によって左右されるべきではない。
■嘲笑する海外メディア
話を元に戻そう。
地球儀問題に対する政府の対応が甚だ見識を欠いていたのは前述の通りだが、マスコミ報道もまた、実に頼りなかった。
全国紙でこの問題を大きく取り上げたのは産経新聞ぐらいで、ほかは社会面の囲み記事扱いだった。とくに朝日新聞は、よほど注意して読まなければ分からないほどのベタ記事で、中国側の圧力があったという肝心な部分すら書いていない。「不適切な表記があった」から「販売を中止すると発表した」と、淡々と報じている。この新聞の中国贔屓は今更言うまでもないが、問題の本質に触れないのは、購読者に対し失礼であろう。
なお、地球儀問題はAP通信とAFP通信が配信し、世界中のメディアが取り上げるところとなった。ワシントンポストをはじめテキサス州の地方紙やオーストラリアの経済誌までもが、日本発の"珍"ニュースを報じた。それほど、国際的な耳目を集める内容だったのだ。教材会社が外国のいいなりになり、国益を損なう地球儀を販売するなど前代未聞だ、というのが普通の国の感覚なのだろう。この感覚が無いのは、日本の政治家とマスコミだけである。
要は、確たる国家意識と正しい歴史認識を持ち合わせているかどうか、という点に尽きる。二世議員が多数を占めるようになった国会には、官僚のように細かな対策について発言する「政策通」は存在するかもしれないが、国家観、歴史観、そして愛国心を持って、本心から「国のために尽くす」と発言し行動する政治家は、実に少ない。
マスコミもそう。年金やガソリン税など個人の利益に直結する問題では大騒ぎしても、国益の何たるかを論じようとしない。自公連立政権や民主小沢体制には辛辣なのに、中国の不遜な横槍には、どこか腰の引けた記事が目立つ。
こうした政治家、マスコミがつくり出す社会的風潮が、一民間企業をして、易々と外国の圧力に屈服させてしまうのだ。
そして、こうした日本の弱点は、冷凍ギョーザ中毒事件でも露呈することになる。
■やられっぱなしの日本外交
ギョーザ中毒事件が発覚したのは一月末のこと。当初からこの事件は、中国側の食品管理の杜撰さに九九%以上の責任があるのは明白だった。だが、日本側が残り一%の確認を慎重にする余り、中国側にいいようにやり込められてしまった感がぬぐえない。
なぜなら日本政府は、中国側の杜撰体質を難詰し、謝罪と賠償を求めるという毅然とした態度を示さなかった。食品衛生法に基づく輸入禁止措置すら、未だにとられていない。四年前に米国でBSE(牛海綿状脳症)牛が見つかった際には、日本国内に人的被害が出ていないにもかかわらず、政府は直ちに米牛の輸入差し止めに踏み切った。BSEより被害が深刻なギョーザ中毒で、どうして同じ対応ができないのか。
民主党の直嶋正行政調会長が二月一日、政府に対して現地調査団の派遣を求めたときも、官邸は「外交問題もあり直ちにとはいかない」と煮え切らず、何とも歯がゆい思いをした。
マスコミ報道もまた、中国批判には慎重のようだ。輸入元のジェイティフーズの検査態勢が甘かったとか、千葉市の保健所の対応が十分でなかったとか、国内のあら探しばかりしている。事件発覚後、全国紙は相次いで社説を掲載したが、いずれも「日中共同で原因解明を急げ」とするものばかりで、中国に賠償を求めたり、輸入禁止を訴えたりする主張はほとんどない。
朝日新聞に至っては、「北京五輪を控えている中国政府にとっても、深刻な事態だろう」と"同情"を寄せつつ、「日本での問題も見過ごせない。とりわけ重いのは、輸入企業の責任だ」とまで言い切っている。
一方、中国側の対応は、例によって素早かった。発覚直後に国家品質監督検査検疫総局と地元警察当局が捜査に乗り出し、わずか一日ほどで、中国の工場に問題はなかったと"断定"。二月二日には工場長と地元検査当局が相次いで会見し、「厳格な安全管理」と「万全の検査体制」を強調。翌三日には日本側に先んじて調査団を来日させた。
日本側がまごまごしている間に、中国側は自らの"潔白"を内外にアピールしただけでなく、調査団派遣により、日本で殺虫剤が混入された可能性もあるとの印象を強く植え付けたのだ。
さらに六日、国家品質監督検査検疫総局は、「中日関係の友好を望まない過激分子の犯行」との可能性を示唆した。
もうお分かりだろう。結論は見えている。中国側に、杜撰な衛生管理を認める気など最初からない。適当な時期に過激分子なるものを逮捕し、その人物の個人的な犯行にしてしまう恐れもある。その際、動機の一つとして挙げられるのは日中関係。もっといえば、過去の日本の侵略行為に対する反感。そして中国側はいう。「犯行は決して許されるものではないが、こうした過激分子を再び生み出さないためにも、日本は歴史認識で、中国や近隣諸国の人々を刺激するような行動をすべきではない」と…。
この杞憂が不幸にして現実のものとなっても、中国側の策略を卑劣の一言で片付けてしまうのは短慮だろう。要は、中国は宣伝工作が上手で日本は下手、ということでしかない。
中国側に遅れて現地調査をした日本政府調査団の原嶋耐治内閣府消費者企画課長は、都合の悪いものは全て撤去された後の工場を視察し、「適切な衛生管理が実施されていると推察された」とコメントした。彼が杉並区の幹部職員であったなら、私は即座に更迭する。
また、冷凍ギョーザを流通させた生協が、未検査の回収商品を勝手に中国側調査団に渡していた。千葉県警が厳重に保管するよう要請していたにもかかわらず、である。中国側が隠蔽工作のため、この商品に細工をしないとも限らない。学研の地球儀問題と同様、国益に著しく反する行為だったと言わざるを得ない。
繰り返す。日本側がまごまごしている間に、中国側は既成事実をどんどん作り上げる。国際社会に向けて、自らの主張を発信し続ける。しばらくして、日本側が実は赫々然々でしたと言ってみたところで、いったん出来上がってしまったイメージは容易に拭えない。すべて後の祭りなのだ。
もしも私に権限があるならば、杉並区内の食料品店への、中国食品の持ち込み禁止措置を、記者会見で発表する。区内の小・中学校から学研教材を閉め出そうとしたように。
■彼の国と付き合うには
六〇七年、聖徳太子が随の煬帝に、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや」で始まる国書を送ったことは有名だが、国書を持参した小野妹子が奏上した言葉は、あまり知られていない。小野妹子は、対等関係を求める国書の内容が煬帝を怒らせるだろうことを知っており、こう言った。
「聞く、海西の菩薩天子、重ねて仏法を興すと。故に遣わして朝拝させ、兼ねて沙門数十人、来たりて仏法を学ぶ」
小野妹子はこの中で、仏法という、当時の東アジア社会の常識、いわば国際ルールを持ち出した。つまり、隋という強大国と面と向き合うのではなく、仏法という国際ルールを通じて、隋と渡り合ったのである。
ここに、古(いにしえ)の先人たちが残した、中国と付き合う上での知恵がある。中国と直接やり合ってはならない、やり合えば必ず飲み込まれる、だから何らかの国際ルールを通じて、間接的に付き合うべきだと、先人たちは教えている。
地球儀問題にしてもギョーザ事件にしても、面と向き合って解決しようとすれば、必ず中国ペースになるだろうし、現にそうなっている。それよりも、国際社会に向けて、日本の正当性と中国の非常識を遍く訴え、中国に対する包囲網をつくっていかなければならない。いざとなれば、中国との取り引きをやめてしまえばいい。そうなって困るのは、日本よりも中国なのだ。
そして、何度でも言う。最終的な決め手となるのは、正しい国家観と歴史観に基づく愛国心から生まれる、国家に殉じるという覚悟であることを、すべての閣僚、政治家は肝に銘じるべきだ。
■隻脚の政治家に学ぶ
ある政治家の事績を紹介しよう。先の大戦で外相を務めた重光葵である。
駐華公使時代の昭和七年、爆弾テロに遭遇して右脚を失った。折しも、第一次上海事変の解決に奔走し、日支両軍の停戦協定が調印される直前の惨事だった。しかし重光は、「停戦を成立させねば国家の前途に取り返しのつかざる羽目に陥る」との一心で、激痛に耐えつつ協定案に署名し、こう詠んだ。
かねてより 国に捧げし命なれば つとめの甲斐を 知るぞうれしき
大戦末期には、木戸幸一内大臣とともに、「鶴の一声(昭和天皇のご聖断)」による終戦工作に尽力した。敗戦後は、米戦艦ミズーリー号での降伏文書調印式に日本政府全権として臨み、こう詠んだ。
願はくば 御国の末の栄行き 吾名さげすむ 人の多きを
二千有余年の歴史の中で、日本が初めて降伏するのである。不名誉極まりない文章に名を残すことを誰もが嫌がったが、重光はその屈辱を一身に背負わんとした。
同時に重光は、今日の日本の有様を、予想していたのではなかったか。すなわち、経済的には豊かになったものの、精神的に堕落してしまった今日の日本を。そして、我々未来の政治家たちに対し、吾が名をさげすめと、叱咤したのではなかろうか。
重光はその後、ソ連の陰謀によりA級戦犯に問われて服役したが、昭和二十九年の鳩山一郎内閣で三たび外相に就任。日本が国連加盟を果たした三十一年の国連総会で、日本全権として国連本部前庭に自ら国旗を掲揚した。
霧は晴れ 国連の塔は輝きて 高くかかげし 日の丸の旗
そして、加瀬俊一初代国連大使に「ありがとう。もう思い残すことはない」と言い残し、一カ月後の三十二年一月二十六日、星の墜ちるが如く急逝した。享年六十九歳。
重光の名をさげすむ時代は、当分きそうにない。